もの書きとしての資料本は〔増殖〕する一方であります。
放送作家→コピーライター→そして現在の時代小説の仕事とそれぞれ資料本は水と油ほどに異なる。
もうひとつ、当初から終始一貫しているコレクションに、演劇・映画(芸能)関係のモノもワンサとある。
仕事場の書斎以外の部屋も本の山なので、先月あたりから思い切って大量処分したのであります。
それで――そのあと本の大移動などをやるのですが、こんどは愛読書や当面必要な本が行方不明になってしまい、発見するまで、ゴソゴソ、イライラ……発掘作業に努める始末なのです。
時代小説書きとしての小生としては〔3−S〕つまり、周五郎(山本)・正太郎(池波)・周平(藤沢)というお三方を畏敬しており、折にふれその作品を熟読玩味しているワケですが、当然、お三方の作品はすぐ取り出せるタナに置いてあります――が、それでもやはり、行方不明になったりします。(ちゃんと戻さない!)
藤沢周平さんのエッセイ集「ふるさとへ廻る六部は」のこと
藤沢周平さんは練馬区大泉にお住まいで、西武池袋線大泉学園の北側。
小生の仕事場は南側でした。駅近くにおなじみの喫茶店があって……なんてこともありました。が、それはそれとして……。
先日は本の整理のあと藤沢さんのエッセイ集「ふるさとを廻る六部は」をあらためて読もうと探したのですが、これが見当たらないのデス。
つまり、ここで引用されていた「ふるさとを廻る六部は気の弱り」というのはダレの句だったのか?ということが気になって、ずっと〔ホン探し〕に努力していたワケです。
2日……3日……4日……と捜索を続けて、遂に発見!そのカンゲキと満足感は筆舌に尽くし難い、なんてオーバーですよネ。
でも、この五・七・五を「検索/名句秀句」等で調べたりとあれこれ作業したあげくのことで、〔発見〕は大カンゲキだったのデス。
――で、「ふるさとを廻る六部は気の弱り」はダレの句か?というと「古川柳」ということを確認しました。
ゴルフは嫌い。競輪・競馬はやらない。マージャン駄目。バー・クラブは大のつくほどキライ。温泉やグルメはめんどうくさいし、そういうもののカネはない。
映画・演劇(あらゆるジャンルのもの)、音楽は大好きでせっせと出かけるが、コレは仕事と関係大ありで趣味とは言えない。
要するに毎日をチマチマしたことで過ごしているつましく、いじらしい男なのデス。
でも、このことをきっかけに周平さんのエッセイを3冊、再々読!
「ふるさとを廻る六部は」(新潮文庫)
「周平独言」(中公文庫)
「小説の周辺」(文春文庫)
「検索/名句秀句」(小学館文庫)
P.S―1「ふるさとへ廻る六部は気の弱り」。
ご存知のように霊場をめぐり歩く六部(巡礼)も体力・気力のおとろえを感じてか、それとなく ふるさとに近いあたりへと立ち戻ってくる――というコト。
じんわりと心にしみる五・七・五ですねぇ。
P.S―2
今年もいつくもの訃報に接しました。
とりわけ、直接にかかわった人への思いもあって――。
加藤和彦さん(元フォーク・クルセダーズ)森繁久弥さん、水の江瀧子さん、そして、飯野知彦さん(デューク・エイセス)。
ご冥福をお祈りします。
P.S―3
12月22日刊で学研M文庫「奈落の銀次始末帖 しぐれ月」が出ます。→詳細はこちら
>
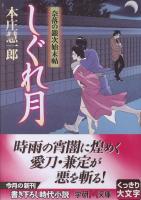
リサイクルエコの原点ともいえる糞尿処理業者――江戸城のトイレから大名・旗本たち、そして長屋の庶民たちの共同トイレの面倒をみる男・葛西の権九郎も、弱き者を助ける奈落の銀次に協力し、ユニークな知恵を駆使してひと役買うというおハナシです。乞うご期待。
そして、2010年1月は、内藤新宿〜新宿コマ劇場クローズまでのノンフィクションもの。(東京新聞出版部)2月は「華屋与兵衛人情鮨 川千鳥夕千鳥」(廣済堂文庫)などなどの予定。
蛇足―4
千とン百冊というホンを整理処分してすぐに、荻窪の笹間書店で10余冊のホンを買い込みました。〔意欲と反省〕が同時進行しています。














