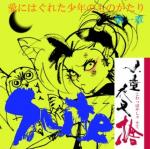愚鈍な人間は、つねに鉄面皮な暴力をふるう。
―― アメリカの詩人・思想家エマーソン(1803〜1882)
***
暴力――この2字熟語から想起される事象にロクなものはない。
その象徴的で究極の「暴力装置」は戦時の日本の軍隊だった。
***
このところずっと、創作のベーシックな資料として、あの「十五年戦争」下における軍隊やその組織に取り込まれた個人について調べている。
***
『「50年目の日本陸軍」入門』より引用する。
【私的制裁について】
リンチのメニューはもりだくさん
激しい訓練を終えて兵舎に戻ってきても、ゆっくり休めるどころか、先述した使役や当番がまわってくる。そうでないものも身の回りの整理整頓は怠ってはならず、靴の手入れや下着の洗濯、銃器の手入れなどで時間が足りなかった。それでも初年兵は、上等兵の分を買ってでもしたのである。
なぜ、そんなにまで古参兵に気を使ったかというと、なによりも私的制裁(リンチ)を恐れたからである。
召集前の若者が兵役逃れに腐心したのも、じつは悪名たかきリンチから逃げたかったのだと書かれた資料もある。それほどリンチは恐れられたのだ。
リンチといっても、ただ殴るだけではない。
たしかにリンチの第一は殴ることだった。「軍隊とは殴るところ」「訓練とは殴られること」といった記述は数多くみられるし、「文字通りの袋叩き、顔といわず頭といわず殴り蹴られ、二等兵の顔は凸凹だった」という記録もある。が、それ以外にも、じつにさまざまの工夫がリンチには凝〈こ〉らされていた。
殴ることを軍隊ではビンタ(関西ではパッチ)というが、このビンタだけでも単純にバチーンッ! とやるビンタに始まり、整列ビンタ、往復ビンタ、上靴ビンタ(革のスリッパで殴る)、帯革〈たいかく〉ビンタ(革のベルトで殴る)、編上靴の靴底(鋲〈びょう〉がうちつけてある)で殴る、鞭〈むち〉で殴る、ゲンコツで殴る、対抗ビンタ等々があげられる。
最後の対抗ビンタというのは、兵隊同士に殴らせるやり方である。たとえば2名にリンチを加える場合、並んで立たせておいて、バシッ、バシッと殴るのがふつうだが、対抗ビンタは、二人を互いに向き合わせて交互に殴らせるというやり方である。
同じ階級の同じ釜のメシを食う仲間だからひどくは殴れない。そんな兵隊の気持ちを知っていながらワザと殴り合わせるわけで、じつに陰険である。さらに、満身の力をこめて殴ってないといって殴る回数をどんどん増やしたりしたそうだ。
兵隊たちにしてみれば、少々痛くても回数が多くても仲間同士でやるよりは、上官に殴られる方が気が楽だったに違いない。
とはいえ、スリッパやベルト、靴底で殴られると、真底こたえたという。
ビンタを始めるとき、まず、
「メガネを外せえ! 歯をくいしばれっ!」
と号令がかかり、次いでバシッとやられるわけだが、この最初の一発の痛さが、とうてい言葉では表わせないほどだとか。
二発目からは単に衝撃だけで、痛みを感じないというのだが、最初の一発の痛みで、おそらく麻痺してしまうのだろう。
それは、そうだろう。スリッパや鋲のうたれた靴底で顔面を殴られるのだ。痛いなんていうものじゃないだろうし、麻痺して当たり前だ。
口の中も切れて血だらけになり、殴られた拍子に血が泡状になってゴボッとふき出る。その兵隊に、「山本一郎が悪くありました」などと謝罪の言葉をいわせようとするのだ。とうてい言葉にならないが、するとまた一発、ビンタがとんでくるという。
リンチのメニューはもりだくさん
激しい訓練を終えて兵舎に戻ってきても、ゆっくり休めるどころか、先述した使役や当番がまわってくる。そうでないものも身の回りの整理整頓は怠ってはならず、靴の手入れや下着の洗濯、銃器の手入れなどで時間が足りなかった。それでも初年兵は、上等兵の分を買ってでもしたのである。
なぜ、そんなにまで古参兵に気を使ったかというと、なによりも私的制裁(リンチ)を恐れたからである。
召集前の若者が兵役逃れに腐心したのも、じつは悪名たかきリンチから逃げたかったのだと書かれた資料もある。それほどリンチは恐れられたのだ。
リンチといっても、ただ殴るだけではない。
たしかにリンチの第一は殴ることだった。「軍隊とは殴るところ」「訓練とは殴られること」といった記述は数多くみられるし、「文字通りの袋叩き、顔といわず頭といわず殴り蹴られ、二等兵の顔は凸凹だった」という記録もある。が、それ以外にも、じつにさまざまの工夫がリンチには凝〈こ〉らされていた。
殴ることを軍隊ではビンタ(関西ではパッチ)というが、このビンタだけでも単純にバチーンッ! とやるビンタに始まり、整列ビンタ、往復ビンタ、上靴ビンタ(革のスリッパで殴る)、帯革〈たいかく〉ビンタ(革のベルトで殴る)、編上靴の靴底(鋲〈びょう〉がうちつけてある)で殴る、鞭〈むち〉で殴る、ゲンコツで殴る、対抗ビンタ等々があげられる。
最後の対抗ビンタというのは、兵隊同士に殴らせるやり方である。たとえば2名にリンチを加える場合、並んで立たせておいて、バシッ、バシッと殴るのがふつうだが、対抗ビンタは、二人を互いに向き合わせて交互に殴らせるというやり方である。
同じ階級の同じ釜のメシを食う仲間だからひどくは殴れない。そんな兵隊の気持ちを知っていながらワザと殴り合わせるわけで、じつに陰険である。さらに、満身の力をこめて殴ってないといって殴る回数をどんどん増やしたりしたそうだ。
兵隊たちにしてみれば、少々痛くても回数が多くても仲間同士でやるよりは、上官に殴られる方が気が楽だったに違いない。
とはいえ、スリッパやベルト、靴底で殴られると、真底こたえたという。
ビンタを始めるとき、まず、
「メガネを外せえ! 歯をくいしばれっ!」
と号令がかかり、次いでバシッとやられるわけだが、この最初の一発の痛さが、とうてい言葉では表わせないほどだとか。
二発目からは単に衝撃だけで、痛みを感じないというのだが、最初の一発の痛みで、おそらく麻痺してしまうのだろう。
それは、そうだろう。スリッパや鋲のうたれた靴底で顔面を殴られるのだ。痛いなんていうものじゃないだろうし、麻痺して当たり前だ。
口の中も切れて血だらけになり、殴られた拍子に血が泡状になってゴボッとふき出る。その兵隊に、「山本一郎が悪くありました」などと謝罪の言葉をいわせようとするのだ。とうてい言葉にならないが、するとまた一発、ビンタがとんでくるという。
(「50年目の日本陸軍」入門 歴史探検隊・著 1991年 文藝春秋刊 pp.107-109)より
現在、「軍隊」という組織は存在しないが、「私刑――リンチ」といえる残虐な行為事象は巷間に拡散した。
***
「核」や「銃器」を前面に押し立てて、治安平和を声高にひけらかす国や政府要人たちのいかがわしさ。
そして、その反面、一向に鎮静化することのない内戦や内紛にともなう一般市民たちの絶えることのない犠牲と辛苦――。
***
鉄は人間を殺さない。殺すのは人間である。
その手は、人間の精神に従う。
―― ドイツの詩人ハイネ(1732〜1809)

ケイちゃんの目 ↓
鉢植えのユズの実を食べにくるヒヨドリ君
カメラでキャッチしにくい野生味の強い鳥です
カメラでキャッチしにくい野生味の強い鳥です



好評配信中 着うたフル・着うた「鳥になれたらいいね」楽曲配信の詳細は
こちら
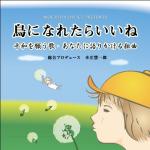
好評配信中 ドラマチック・リーディング「小童夜叉・捨」
配信詳細はこちらを ![]() ご覧ください。
ご覧ください。