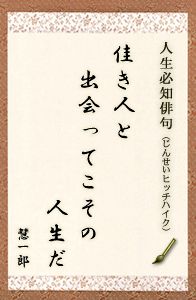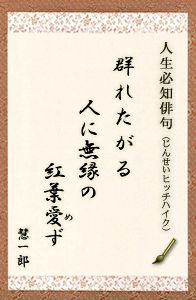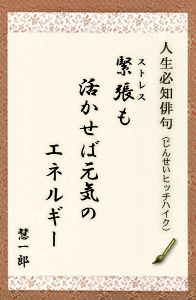樋口恵子さんへの手紙
テレビのワイドショーとやらの番組には、評論家と称する方が大勢出演なさっている。ヒョーロンカというよりヒョーロクダマといったほうがいい雑感屋ばかりだ。しかも皆さんエラソーに喋っている。
さてここでは、4分の1世紀以前からの知己、社会評論家の樋口恵子さんのことにふれてみたい。
いま樋口さんは、婦人問題、高齢者福祉問題、教育問題と幅広く活躍する「信じられる評論家」である。樋口さんとは、彼女が東大の学生だった20歳のときに知己を得た。
それはたしか読売新聞が主催した成人の日(当時は1月15日)を記念する「はたちの記」の論文募集で樋口さんが学生の部第一席になられたことがきっかけだった。
昭和26(1951)年のことである。樋口さんは旧姓柴田さんといった。
わたしは便せん10数枚に感想をしるして送った。そのころのわたしは、身辺事情から進学を断念、父親の仕事をいやいや手伝いながら演劇を志していた。その苛立ちや、学生に対するある種の羨望が入りまじった、少々偏屈な意見だったといまにして思うのだが。
しかし、樋口さんからは謙虚で柔軟性に富んだご返事が届いた。
いま手元に樋口さんがご恵贈くださった著書がある。(「私は13歳だった/少女の戦後史」筑摩書房)そのご本に私との出会いのことがしるされているので引用させて頂く。 (文中の望田市郎はわたしの本名である)
以下「私は13歳だった/少女の戦後史」筑摩書房より引用
「青い実の会」とのであい
はたちの記念に投稿という決意表明をしたのはいいが、だからといって自分の行き方が確立するはずもなく、あいかわらず浮き足立った迷いの日々の連続だった。メディアの少なかった時代、周辺「学内有名人」になってしまい、みんなに「おごれ」「おごれ」といわれたのがオチであった。「幼稚っぽいこと考えてるんだなァ」と軽蔑のまなざしを向ける仲間もいて、今後、金輪際投稿のようなことはするまいと、心から誓った。
とはいえ、今となってはいくつかの副産物があった。全国からの感想文が、ファンレター的なものから辛口批評まで、優に段ボール箱一つ分届いた。みんな目を通し、心に残った手紙には簡単な礼状を書いた。その中で、本ものの論文以上に力を入れて返事を書いた手紙があった。望田市郎という、四角い文字の手紙は、私と同年、つまりはたちを迎えた青年からのもので、高等小学校(今の中学と思えばよい)を卒業後、町工場で働く労働者と名乗っていた。私は「あなたのお便りに、お調子ものの私はガーンとハンマーで一撃を食らった思いでした」と書きはじめた。
「青い実の会」とはいわば文学サークルのようなもので、小学校の同期生を中心にした集いであった。
わたしはいまもって《毛並み》とか《育ち》といった言葉が嫌いだが、しかし、樋口さんからのお手紙の文章を読んでいて、その嫌いな二つの言葉を、あらためて羨望をまじえた気持ちで反芻したものだ。
このひとは《聞く耳を持っている》ということも強く心をうった。
次回でもう少し樋口さんの文章を紹介させて頂くが、樋口さんはもうひとつ、わたしに《重要なきっかけ》をプレゼントしてくれたのである。